職業体験レポート~陶磁器づくりin波佐見~

取材・文=みゆう(N高5期・ネットコース)
写真=参加した生徒・スタッフの方々
2022年度から復活した宿泊型職業体験。
その職業体験の1つ、「陶磁器づくり職業体験」に参加してきました!
この記事では、実際に参加してみての感想も交えながら、職業体験の内容を紹介していこうと思います。
「陶磁器づくり職業体験」とは?
記事の内容に入る前に、職業体験の概要を紹介しようと思います!
「陶磁器づくり職業体験」とは、2022年11月に開催された、長崎県の東彼杵郡波佐見町(ひがしそのぎぐん、はさみちょう)という場所で、伝統的な焼き物「波佐見焼」について学び、体験できるプログラムです。
開催日数は4泊5日と、数ある職業体験の中でも特に期間の長いプログラムであるため、よりじっくりと波佐見焼について学ぶことができる上、参加生徒との絆も一層深まるような時間が過ごせます。
1日目
5日間の長い職業体験は、「長崎県窯業技術センター」という場所からスタートしました!
日本各地から集まった総勢20名の参加生徒とも、ここで初めて実際に会うこととなります。
開校式を行い、その後は窯業技術センターの方から「長崎県の陶磁器産業について」や「技術センターが行っていること」などの説明を受けました。
また、波佐見焼が出来上がるまでの工程も教えてくれました。
ここで、波佐見焼が出来上がるまでの流れを簡単に説明すると、
・型づくり
↓
・生地づくり
↓
・素焼き
↓
・絵付け
↓
・釉薬(ゆうやく)
↓
・焼成(しょうせい)
という流れになっており、この作業を型屋、生地屋、窯元と呼ばれる3つが役割分担し、「分業制」で行います。
実は日本の日常食器の約16%はここ、波佐見町で作られているそうなのですが、その波佐見町の人口は1万5000人程度。
そんな小さな町で大量生産が可能な理由の1つが、この「分業制」なんです。
今回の職業体験では、生地づくり〜焼結までを実際に見学・体験しながら学びます!
細かい作業内容についてはこの後の体験紹介(2日目以降)で簡単に説明しつつ、体験の様子を紹介していきます!
説明を受けた後は、窯業技術センター内を見学していきます。
センター内には様々な形の陶磁器があり、中には光をつけると写真が映し出されるものや、3Dデータを活用して細かいところまで精密に作られた陶磁器などもありました。
陶磁器=食器のイメージが強かったので、こんな不思議な陶磁器があることに驚きました!
夜は懇親会を兼ねたちょっと豪華な夜ご飯。
実はこの食器、波佐見焼なんです!
食事を通して波佐見焼に触れ合うというのも学びの1つということで、これから5日間一緒に過ごす人達との仲も深めながら食事を楽しみ、1日目は終了しました。
2日目
2日目からはいよいよ本格的に陶磁器づくり体験がスタート!!
まずは生地づくりの工程から体験!
生地づくりは、波佐見焼が出来上がるまでの工程の2番目、型づくりの次の工程です。
生地屋さんでは、型屋さんが作ってくれた石膏で出来た「型」の中に泥しょう(でいしょう)と呼ばれる液状の土を流し込んで成形を行います。
最初はドロドロだった泥しょうも、石膏型が余分な水分を吸って固まってくれるので、短時間でしっかりとした形に形成されます。
1つの焼き物を作り上げるために、何種類もの型を使っていくつものパーツを作り、それを削ったり、くっつけたりすることで、コップやお皿などの簡単な形のものはもちろん、急須のような少し複雑な形のものも作り上げることができます。
陶磁器や陶芸と聞くと、ろくろで作るところを思い浮かべる人が多いと思います。
波佐見焼でもろくろを使って作る方法もありますが、このように型を使用することで比較的簡単に、そして一度に複数作れるため大量生産しやすく、その結果安価で売れることが波佐見焼の特徴です。
とはいえ、まだ固まりきっていない生地の形を崩さないように整えたり、パーツを組み合わせたりすることは、素人の私にとってはかなり難しかったです。
また、急須などの複雑な形のものは出来上がるまで完成形のイメージがつかず、「今はどこのパーツを作っているのか?」「これはどこにくっつければいいんだろう?」と終始戸惑いながら作っていました…….(笑)。
その分、完成形まで作れた時は大きめのジグソーパズルを最後までやり遂げた時のような達成感がありました!
お手本のように綺麗に作ることは出来ませんでしたが、とても楽しかったです!
3日目
3日目は、窯元という場所で行われる工程(素焼き~焼成)の体験とろくろ体験をしました!
窯元では、生地屋さんで作った生地を一度約900℃でじっくりと焼く「素焼き」という工程を済ませたあと、絵付けを行います。
絵付けは写真のように手描きで行う場合もあれば、量産に適した「パッド印刷」や「判子」などが使用されることもあります。
また、波佐見焼では基本的に「呉須(ごす)」と呼ばれる藍色の絵の具が使用されますが、現在ではカラフルな色の絵の具が開発され、多様な商品展開がされているみたいです!
絵付けを行った後は、「施釉(せゆう)」という「釉薬(ゆうやく)」をかける工程を行います。
釉薬とは、陶磁器の表面を覆う薄いガラス質のことで、これをかけると陶磁器につやが出ると共に、耐水性が高まり、汚れにくくなります。
釉薬は液状の時は白く濁っていますが、焼くと透き通った透明になります。
釉薬をかけた後に十分乾燥させたらいよいよ焼成、仕上げの焼きの工程に入ります。
焼成ではおよそ1300℃で約15時間かけてじっくりと焼き、そこからまた15時間かけてゆっくりと冷まして完成となります。
窯元で意外だなと思ったのですが、職人のような人が沢山いるわけではなく、むしろパートと見受けられる人が多かったことに驚きました。
窯元の中でも絵付けをする人、釉薬を付ける人など、「分業制」を取り入れることでそれぞれの作業が簡易化されるため、職人さんたちが1つ1つ作るというよりは、工場のように複数人で複数の商品を作るという感じでした。
今回の職業体験では、この窯元での工程を約3時間かけて体験させてもらいました。
体験といっても、実際にそこで働いている人たちと同じ作業をさせていただいたので、まるで本当に自分がここで働いているかのようなリアリティを感じることができて、すごく貴重な体験となりました!
窯元体験の後は、ろくろ体験!!
陶芸といえばろくろ、ということで、私自身もこのろくろ体験を一番楽しみにしていました。
今回の職業体験では、お茶碗を作りました!
みんなドキドキした様子で、土に触っていきます。
職人さんに教えてもらいながら、少しずつ力を加えて、形を作っていきます。
なかなか思い通りの形にならないことに悪戦苦闘しながらも、各々自分なりのお茶碗を作り上げていきました。
ちなみにこの時作ったお茶碗は、後日焼いて家に届けてくれました!
ろくろ体験の時間に作ったのはお茶碗のみでしたが、「もっとろくろをやってみたい!」と思った私はこの後の自由時間もろくろを使わせていただきました。
何かを作るというよりは適当に土いじりができれば十分だったのですが、途中職人さんが、「ここをこうしたら平皿のような形にできるよ」「この形からだったら一輪挿しが作れるからやってみようか」と、片付け中だったのにもかかわらず丁寧に教えてくれて、平皿と一輪挿しを作ることができました!
そして最後に、なんと土をこねる体験もさせていただきました!
ろくろで何か作る時も、こねる時も、土が思い通りにならなくてかなり難しかったですが、無心で土を触る時間は私にとってとても安らぎの時間になり、すごく楽しかったです!
4日目
4日目は丸1日グループワークの時間です。
実は今回の職業体験、体験するのは陶磁器づくりだけではありません。
陶磁器に関する体験の時間とは別に、1日目~5日目まで毎日、「オリジナルデザインのマグカップを作ろう!」というグループワークがありました!
4つの班に分かれ、各班1つずつオリジナルデザインのマグカップを作ります。
もちろんマグカップは波佐見焼で作られたものです。
といっても、ただ単に好きなデザインを作るというわけではなく、「実際に売ること」を想定してデザインを考えていきます。
デザインを考えていくときも、最初からデザインの作成を行うのではなく、ペルソナから考えていきます。
※ペルソナとは、商品の典型的なユーザー像のことで、年齢、性別、趣味、性格、ライフスタイルなど、リアリティのある詳細な情報を設定していくこと※
「年齢は10代ぐらいかな? 私達と同世代の方が考えやすいよね。」
「それならN/S高生にしちゃった方がいいね。」
「趣味はどうする?」
「アニメ鑑賞とか? どうせならオタクにしちゃおうよ!」
などを話し合いながら、ペルソナを考えていきました。
ペルソナが決まった後は、「そのペルソナにマグカップを売るためにはどういうデザインにすればいいか?」を考えます。
「ペルソナの好みやニーズに合っているかな?」
「テーマはどうしよう?」
「せっかくなら波佐見要素も入れたいよね。」
「波佐見要素ってなんだろう? ちょっと波佐見焼について振り返ってみようか。」
と、各班頭を捻りながらデザインを固めていきます。
このデザイン固めが想像以上に難しくて、非常に難航しました。
振り返って見ると、私は今まで「自分が好きなもの・作りたいもの」でデザインを考えたことは何度がありましたが、「売ることを考えて、売る相手のニーズに合ったデザインを作る」ということ、いわゆるマーケティングはしたことがありませんでした。
「こういうデザインが作りたい!」と思っても、ペルソナの好みに合っていなかったりすると「売るためのデザイン」ではなくなるし、逆に「売るためだけに考えたデザイン」にすると自分の好みではなくなってしまってちょっと納得がいかなかったりと、自分の気持ちに折り合いをつけるのも難しかったです。
最後の方は疲れ果てて寝ちゃう人も……(笑)。
各班苦戦しながらも、最終日までにはデザインを作り上げることが出来ました。
5日目
最終日である5日目に行われた閉校式では、グループワークで作成したオリジナルデザインのマグカップを班ごとに発表していきます。
かつて波佐見焼を作る際に使われていた、「登り窯」をイメージしたデザインを取り入れたり、
SNSでお馴染みの「ハッシュタグ」を使ったデザイン。
シンプルなのに可愛くて癒されるデザインに、
完全オリジナルロゴを入れたデザインまで!!
全く違った個性と良さを持ったマグカップが、計4種類出来上がりました!
どのマグカップもとっても素敵で、「全部ほしい!!」と思うぐらい魅力的でした。
このマグカップ紹介を最後に、今回の職業体験は終了となりました。
陶磁器や波佐見焼についてだけでなく、「売るための商品を作ってみる」という体験もできた陶磁器づくり職業体験、とっても楽しかったです!!
最後に
陶磁器づくり職業体験レポート、いかがだったでしょうか?
「職業体験楽しそう!」
「マグカップほしい!」
と思ってもらえたなら幸いです。
ここまで読んでくださった皆様に1つ、重大なお知らせがあります。
なんと…………
今回の職業体験で作ったマグカップが、磁石祭2023で発売されます!!!!!!
価格はどれも1000円!!
在庫も各班100個(一部200個)という大盤振る舞い!!!
当日の販売も、今回の職業体験に参加した生徒が行います!
磁石祭に参加する予定の方は、是非立ち寄ってみてください!!
最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
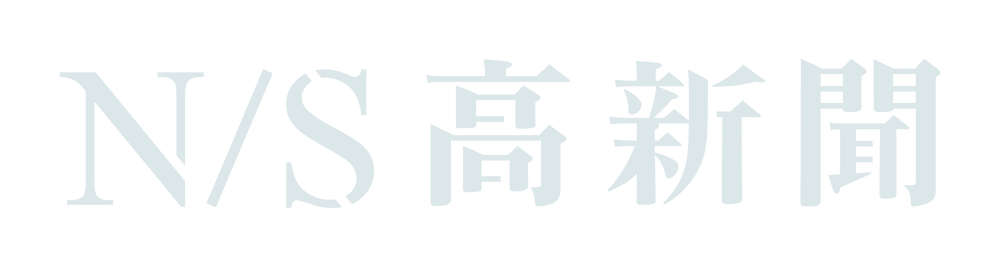


コメント